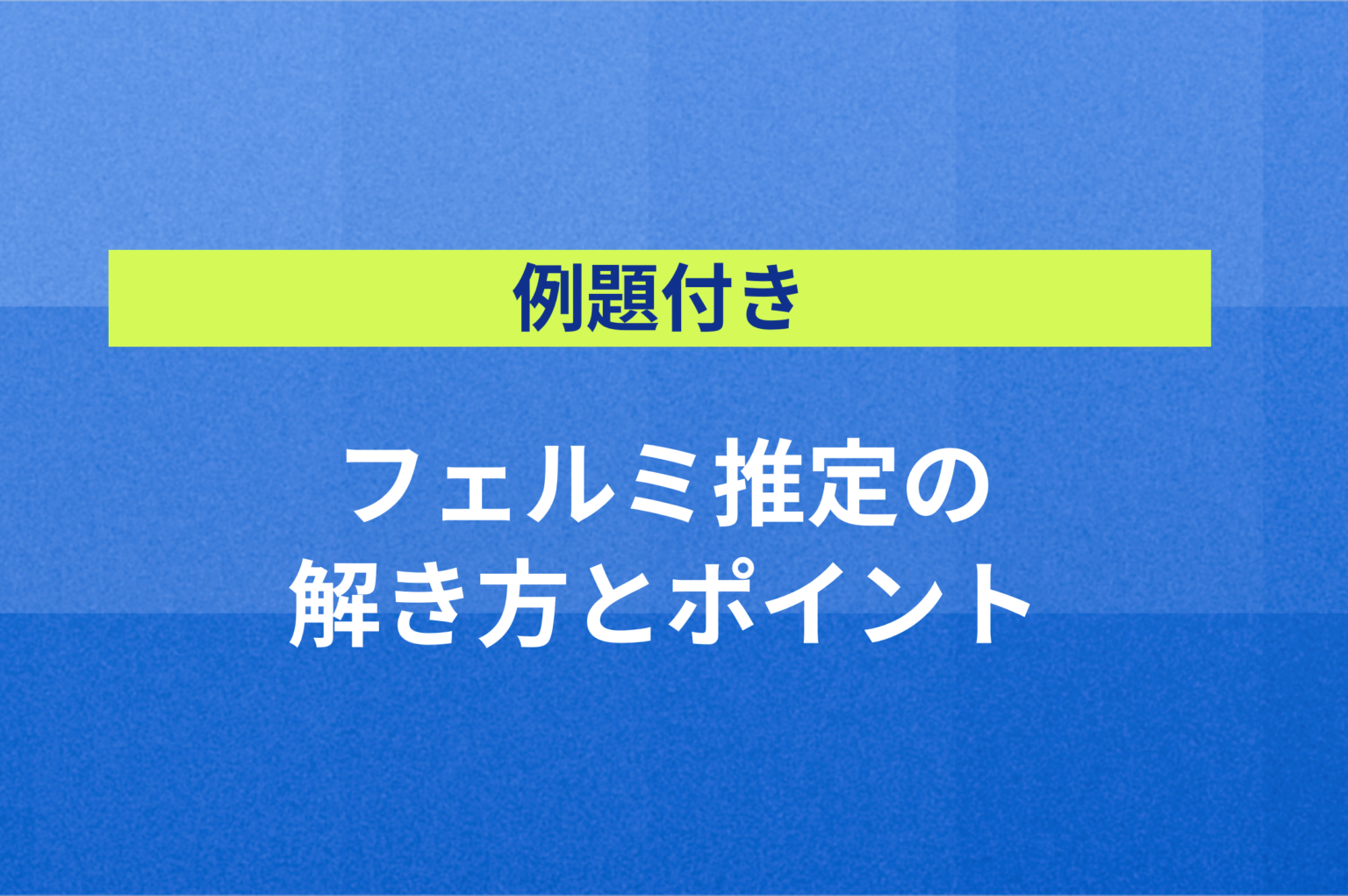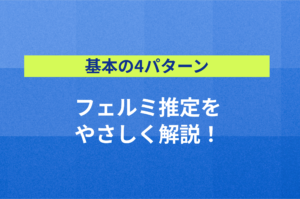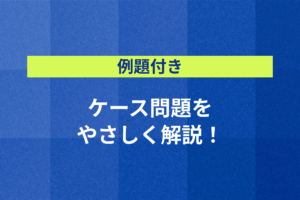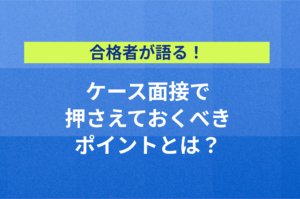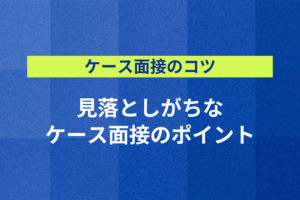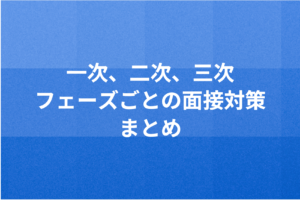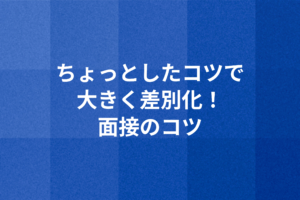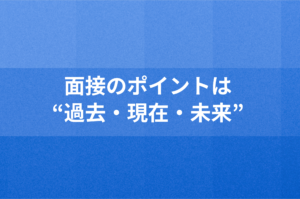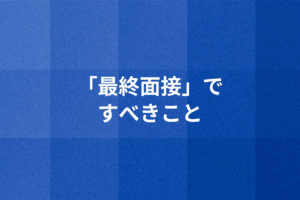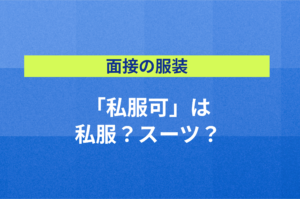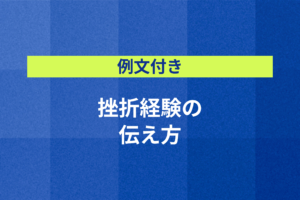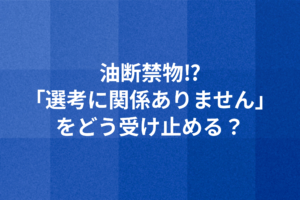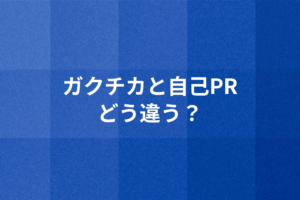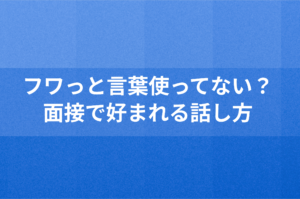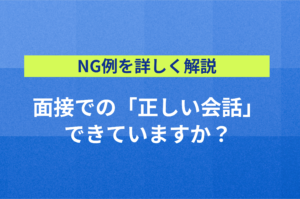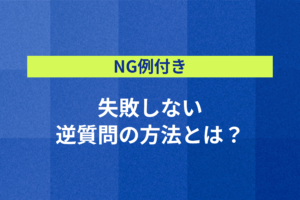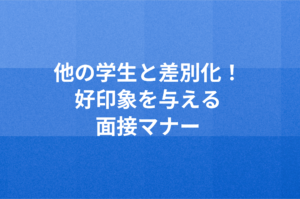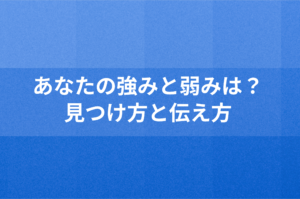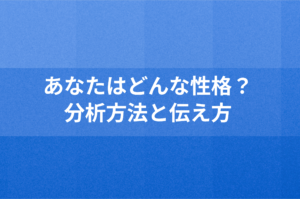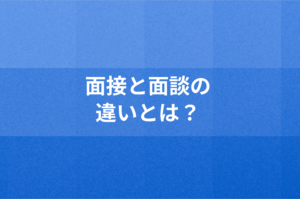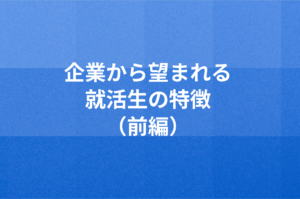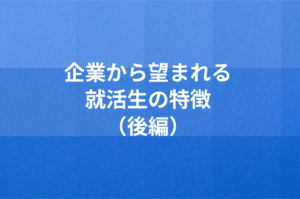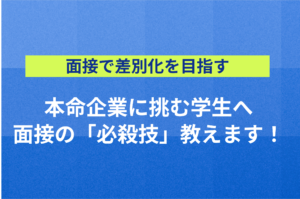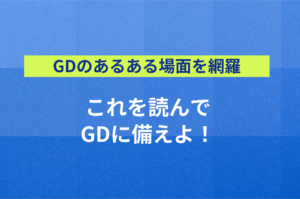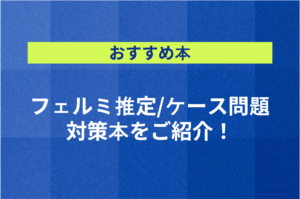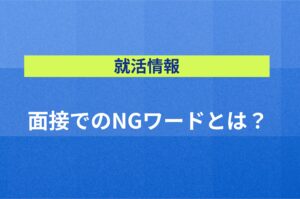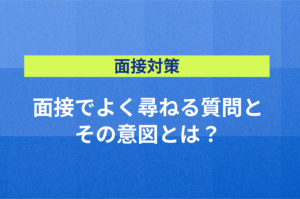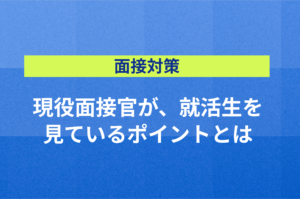はじめに
近年、フェルミ推定は多くの企業の入社試験や面接で出題されるようになっており、就活生にとって避けて通れないテーマの一つです。とはいえ、
・「どう対策すれば良いかわからない」
・「そもそもどのようなものかイメージが湧かない」
といった不安を抱いている就活生も多いと思います。
そこで今回は「フェルミ推定とは何か?」という基礎から、実際の例題を通じた解き方、覚えておくべきポイントまで丁寧に解説します。
コンサル業界を志望している方は必見の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください!
参考文献
・「数学的センス」を磨く フェルミ推定 –
・就活サイト【ワンキャリア】
フェルミ推定とは?
フェルミ推定とは「正確な値を得ることや実際に調査することが困難な数量を、わずかな情報や値をもとに論理的な推論を進め、短時間で定量的な概算をすること」(デジタル大辞泉)を言います。簡単に言うと「だいたいの値」を論理的に見積もる手法のことです。
実際に出題されたテーマ
- 「日本にある電柱の本数は何本か?」
- 「インターネット上のすべてのwebページ数は?」
このような予想もつかない問題が面接で出題されます。
フェルミ推定のポイントは「正確な答え」を導くというより、どのように考え、どのように答えに至ったかという“思考のプロセス”が評価されるという点にあります。
フェルミ推定で覚えておくべき基本数値
フェルミ推定では、最低限の基本的な数値知識が必要不可欠です。
以下に就活生が押さえておきたい代表的な15項目を紹介します。
- 日本の人口:約1.2億人
- 東京都の人口:約1,400万人
- 日本の世帯数:約5,000万世帯
- 1世帯あたりの人数:平均約2.3人
- 高齢者人口(65歳以上):約3,600万人
- 子ども人口(15歳未満):約1,500万人
- 出生数:約72万人
- 大学生の数:約290万人
- 高校生の数:約300万人
- 日本全国の小学校数:約2万校
- 日本全国の大学数:約800校
- 大学進学率:約50%
- 大企業の数:約1.2万社
- 中小企業の数:約420万社
- 日本人の平均給与:約430万円
これらの数値はあくまで目安であり、フェルミ推定では「おおよそこれくらい」と仮定しつつ、整合性のある推定を構築することが重要です。
フェルミ推定の手順
フェルミ推定の手順は以下の6つで構成されます。
- 問題の発見(情報整理)
- 思考実験(具体化)
- 要素の洗い出し(分解)
- モデル化(抽象化)
- 計算(数値化・算出)
- 結果とプロセスの提示(説明)
それでは、この手順に沿って実際の例題を解いてみましょう!
例題:日本の年間書籍売上はいくらか?
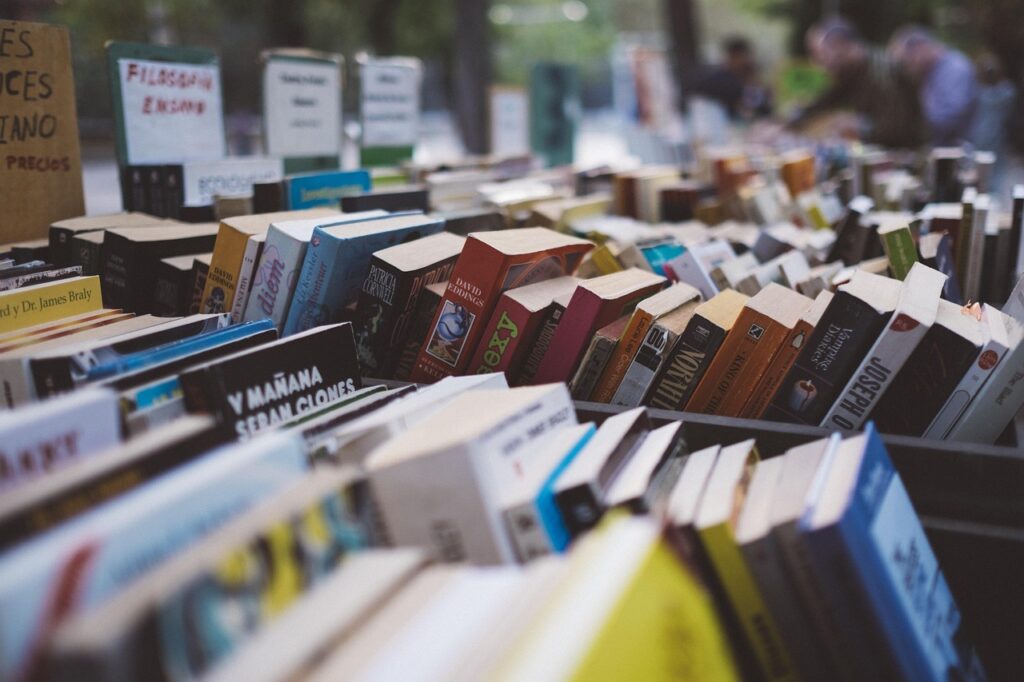
①問題の発見(情報の整理)
②思考実験(具体化)
書籍の売上を推定するために、まず必要な情報を整理します。できるだけ具体的にイメージしてください。
たとえば:
- 書籍はどこで、どのような人が購入していますか?
- 書籍の価格は?
- 書籍を買う人はどれぐらいいますか?
- そのような人たちは年間どれくらい購入していますか?
書店に立ち寄る人や、SNSで読書記録を投稿する人など、自分の経験や観察からイメージを具体化すると、この後の手順がスムーズになります。
③要素の洗い出し(分解)
①と②を通じてイメージを膨らませたら、「日本の年間書籍売上」を決定する要素をできるだけ細かく分解していきます。
- 日本の人口
- 読書習慣がある人の割合
- 書籍1冊あたりの平均売値
- 読書習慣がある人1人当たりの年間購読数
最初は難しいかもしれませんが、求めたい推定量が「何によって決まるのか」を分析し、いくつかの要素に分解していきましょう。
④モデル化(抽象化)
③の分解で洗い出した要素を組み合わせて、推定量を求めるための計算式をつくります。今回の場合は以下の通りです。
日本の年間書籍売上(円/年)
=日本の人口(人)×読書習慣がある人の割合
×書籍1冊当たりの平均売り値(円/冊)
×読書習慣がある人一人当たりの年間購読数(冊/人・年)
⑤計算(数値化&算出)
推定に必要なデータと推定量は以下の通りです。
- 日本の人口:
おおよそ1億2000万人 - 読書習慣がある人の割合:
活字離れが進んでいると言われていますが、子供からご年配までの読書習慣のある人は少なくありません。そこで、読書習慣がある人の割合は70%と仮定します。 - 書籍の価格:
週刊誌やコミックなら500-800円、単行本なら1,500円前後で、かなり開きがありますが、ここでは書籍1冊あたりの平均売値を1,000円ということにします。 - 読書習慣がある人1人あたりの年間購読冊数:
個人差が大きく、毎週決まった雑誌を買う人もいれば、1年に1~2冊という人もいるでしょう。そこで、読書習慣がある方は月に1~2冊購入するとして、年間では20冊ということにします。
以上を踏まえて算出すると、以下の通りになります。
日本の年間書籍売上(円/年)
=日本の人口(人)×読書週間がある人の割合
×書籍1冊当たりの平均売り値(円/冊)
×読書習慣がある人一人当たりの年間購読数(冊/(人・年)
=12,000万(人)×70(%)×1,000(円/冊)×20(冊/人・年)
=16,800億(円/年)
⑥結果とプロセスの提示(説明)
フェルミ推定で結果を伝える際は、数値そのものだけでなく、その数値に至るまでのプロセスを丁寧に説明することが大切です。「答えは〇〇くらいです」と伝えるだけでは、受け手が十分に納得感を得られず、結果に対して疑問が残ることがあります。相手の信頼を得るためにも、また議論を深めるためにも「なぜそう考えたのか」「どういう前提や計算で導いたのか」を明確に示しましょう。そうすることで、建設的なフィードバックが得られるだけでなく、自分自身の思考を客観的に振り返ることができ、より精度の高い推定につなげることができます。
問題に挑戦!
では最後に、ここまでのポイントを踏まえてフェルミ問題に挑戦してみましょう!
例題:社員数100人の会社で「ペーパーレス化」をすると年間のコストカットはいくら?
まずは以下のような観点から、コスト削減の要因を洗い出してみましょう。
- 印刷コスト:1人あたり年間で何枚印刷し、1枚あたりいくらかかるか?
- 用紙代:A4用紙1枚あたりのコスト(例:0.5円)など
- プリンタの維持費・トナー代:1年にどれくらいかかる?
- 紙の保管スペースの賃料:紙を保管するためのスペースにどれくらいコストがかかっているか?
たとえば、
- 「1人あたり月に500枚印刷する → 年間6,000枚」
- 「印刷コストは1枚あたり5円」
という前提を置けば、印刷だけで1人あたり年間3万円、100人で300万円のコストになります。
さらに、紙の保管室がある場合はそのスペースが不要になり、月5万円の賃料がなくなるとすれば年間60万円の削減となります。
このように、コスト要素を1つずつ分解し、前提を置いて試算していくのがフェルミ推定の基本です。ぜひ、自分なりの仮定をおいて考えてみてください!
いかがでしたでしょうか。
フェルミ推定は、「正確な答えを出す」ことよりも、「いかに筋道立てて論理的に考えられるか」が評価されます。たとえ推定値に誤差があったとしても、丁寧に振り返りを行えば、改善ポイントが明確になり、スキル向上につながります。就活の場だけでなく、コンサルやビジネスの現場でも応用できる重要な思考技術ですので、ぜひ継続的に練習してみてください。
こちらの記事をご覧になり、少しでも役に立ったと思っていただけると幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
<執筆:山崎 誠英>
※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。