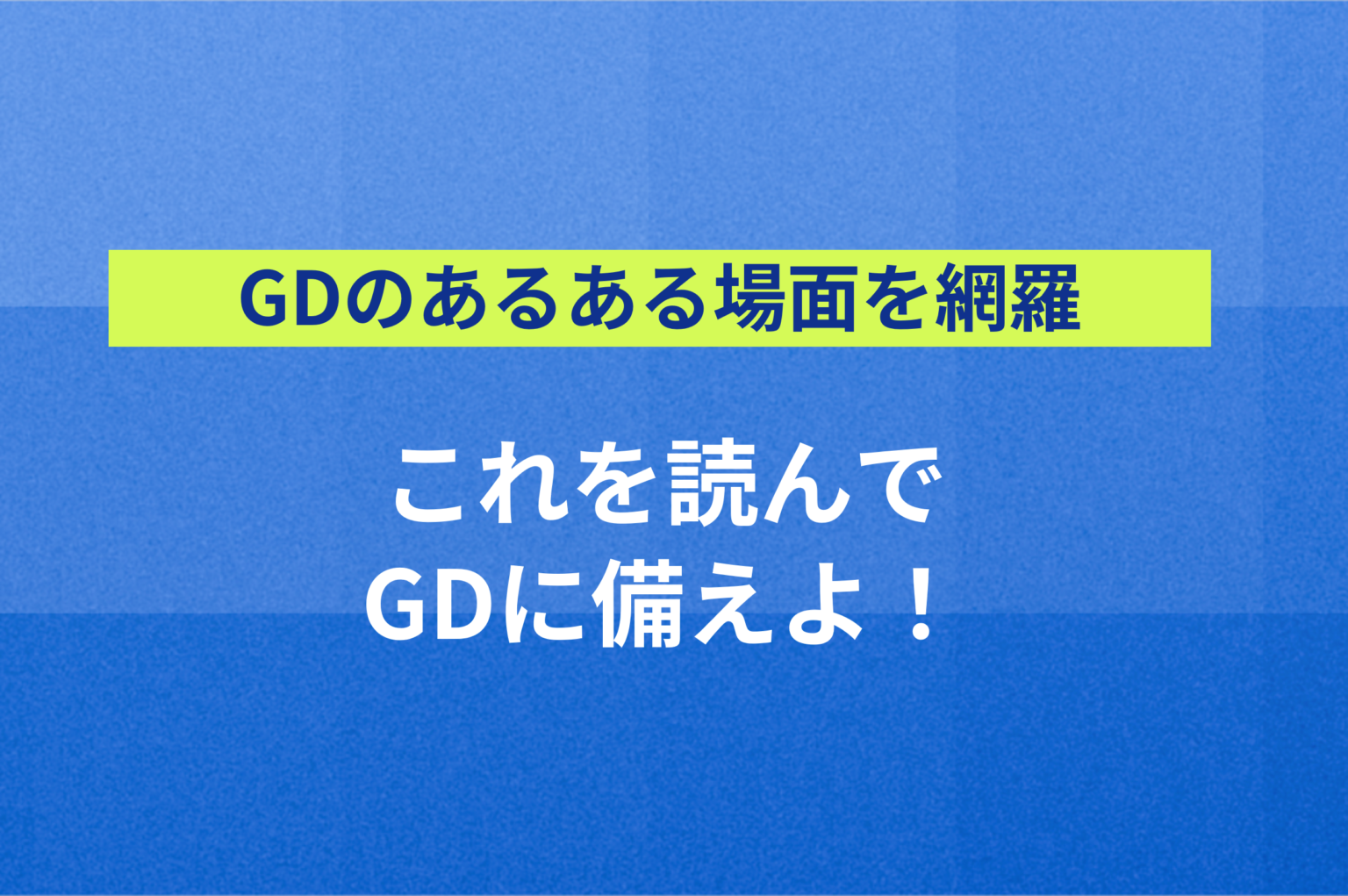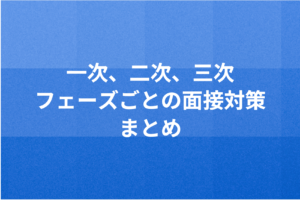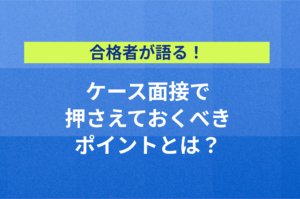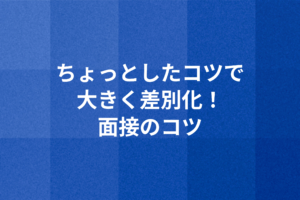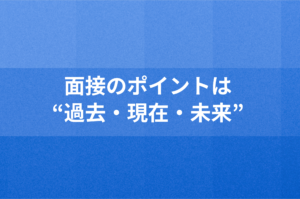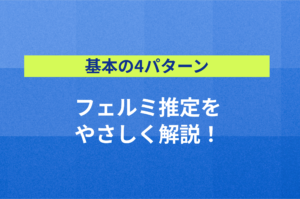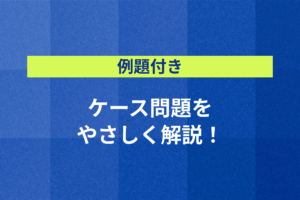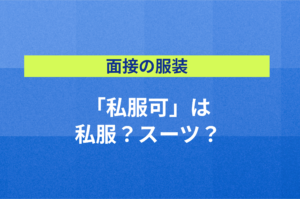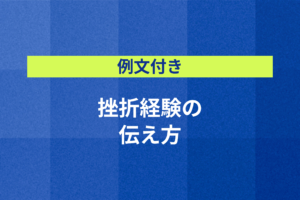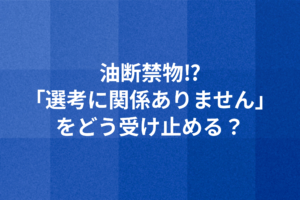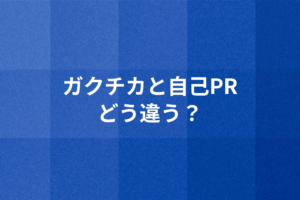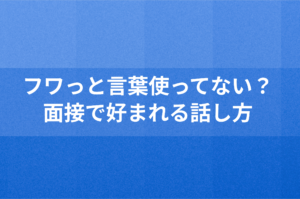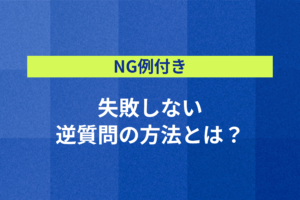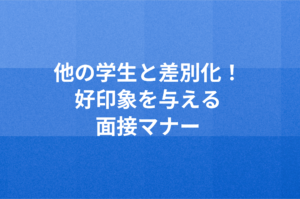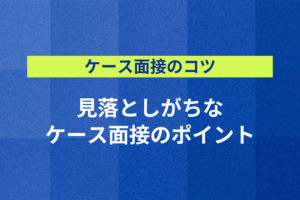今回はコンサルティング会社内定者や現役就活生が実際に体験したグループディスカッション※場面をもとに、GDで遭遇するぶつかりがちな場面を想定し、コンセプチュアル・スキルを用いてその場面をどのように乗り越えていけば良いのかについて考えていきましょう!
※「グループディスカッション」を「GD」と呼称します。
Chapter.1 GDの基本
まずは、GDの基本についておさらいしましょう。詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!
▼GDのコツについての詳しい記事(前編)はこちら
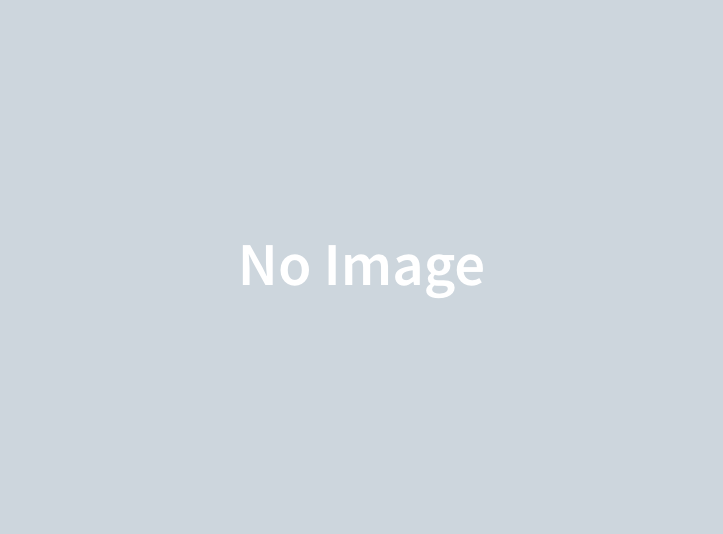
https://www.wantedly.com/companies/zein/post_articles/191985
▼GDのコツについての詳しい記事(後編)はこちら
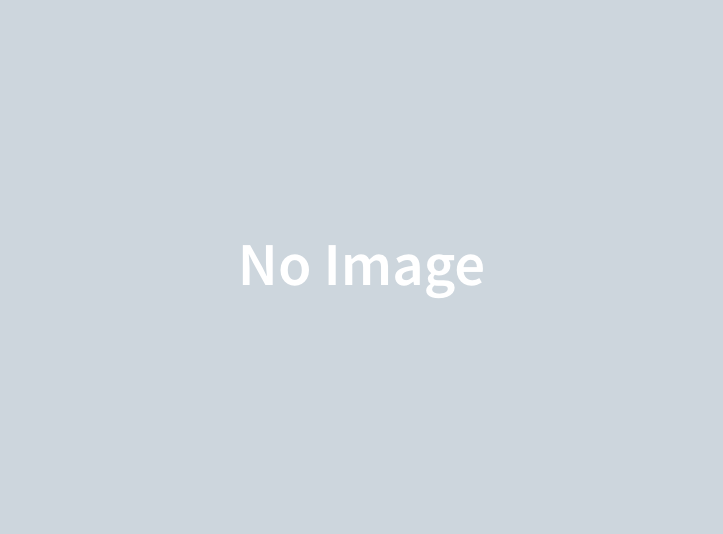
https://www.wantedly.com/companies/zein/post_articles/192282
GDを通過するためには、企業が就活生を評価するポイントを把握し、逆算して臨む必要があります。全ての企業が同一の評価基準を設けているわけではありませんが、特に新卒採用のGDで重視されることが多いのはチームワークです。何故なら、企業は人間の集合体であり、実際の仕事でもチームプレーが要求されるためです。
チームワークとはチームの総合力を上げるために意識すべきもので、それに必要な要素は、① 目標共有② 適性把握③ 役割分担の三つです。
まず、目標共有に関しては、メンバー全員が同じ方向を向くために必要です。適正把握と役割分担に関しては、各メンバーが得意なことや持ち味を発揮し、他メンバーの力と組み合わせることで、最適化することができるため、必要だと考えられます。
またGDでは、限られた時間の中で複数のメンバーが意見を出し、一つの成果物にまとめることが求められます。各人が合理的に思考・行動して上記①〜③を行い、チームワークを活かして議論することができれば、個人が出すことのできる成果の合計より大きな成果をチームとして出すことができます。
しかし、実際にチームワークが完璧に機能することは稀です。何故なら、GDに参加するまでの背景は就活生によって千差万別であるためです。学生時代の過ごし方やGD経験の有無など、異なる背景を持った就活生がいることで、準備をしていた就活生にとっては不確実な事態が起こる可能性があります。
GDの定石に則り議論を円滑に進行させることだけが、チームワークの達成として評価される要素なのでしょうか。私はそうではないと考えています。確かに、議論を円滑に進行させるに越したことはありません。しかし、どんなにGDの方法を勉強してもGDで壁に当たることは、面接官も理解しています。
経営学者カッツによると、企業の考える有能な人材とは、コンセプチュアル・スキルを持つ人間です。コンセプチュアル・スキルとは、複雑な事象を分析して変化を予測し、問題を対処する能力を意味します。つまり、この能力を持つ人材は、不確実性に対応する能力に長けていると考えることができます。そうであるならば、GDにおける不確実性は、企業の求める人材が持つコンセプチュアル・スキルの見せ所です。コンセプチュアル・スキルは、以下の10要素により構成されています。
【コンセプチュアル・スキルの10要素】
①ロジカルシンキング
②ラテラルシンキング
③クリティカルシンキング
④多面的視野
⑤受容性
⑥柔軟性
⑦知的好奇心
⑧探究心
⑨チャレンジ精神
⑩俯瞰力
Chapter. 2では、これら10要素をどのようにアピールし、不確実性に対応するのかを考えていきます。
Chapter.2 あるある場面の対応策
Chapter. 2では、実際にGDの中でどのような壁にぶつかるのか、それにどのように対応すべきかを考えていきます。今回は、以下の4場面を紹介します。
ケースA:適切な議論の進め方から逸脱しそうになった時
ケースB:自分がアピールしたい役割やキャラクターが他人と重複した時
ケースC:メンバー全員が同じ方向を向いて議論できていない時
ケースD:議論の進行が滞った時
これらの場面はコンサルティング会社内定者や現役就活生が実際に体験した場面です。では、各場面の紹介と対応方法について、コンセプチュアル・スキルと対応させながら考えましょう。
ケースA:適切な議論の進め方から逸脱しそうになった時
具体的には、以下の場面が挙げられます。
- アイディアベースの議論が始まってしまう場面
- 前提確認の時に具体的な施策の議論になってしまう場面
テーマにも依りますが、GDの練習や予習をしている就活生は、定石の進め方を知っていることでしょう。
課題解決型のテーマを例に挙げると、以下の進行が一般的です。
1. 前提確認
2. 現状分析
3. 解決策立案
4. 施策評価
しかし、GDの経験や知識が足りない就活生は、その流れを理解していない可能性があります。その場合、チーム全体が適切ではない進行方法をとってしまう可能性があるほか、理解している就活生視点では、思い通りに議論が進まないストレスが生じるかも知れません。そのため、このような場面は、適切な進行方向からの思いがけない脱線という意味で不確実な状況です。
このような状況を打破するためには、コンセプチュアル・スキルの①ロジカルシンキング、②受容性の2つの要素を活用することが有効です。
①ロジカルシンキング
ロジカルシンキングに関しては、論理的に議論の流れを考えていることをメンバー、面接官に伝えるために有効だと考えられます。先に例として挙げた進行方法は、誰かが勝手に決めたものではなく、限られた時間内でのアウトプットから必要なことを逆算し、一般的に用いられています。
1〜4の行程を覚えてGDに臨むことは簡単ですが、なぜそのような流れが出来上がっているのかを理解している就活生は、私の体感ですが、少ないのではないかと思います。そのため、流れの背景を理解していることの提示は、ロジカルシンキングでの差別化に有効ですし、他のメンバーを納得させることもできるでしょう。
発言例:
「最終的に求められている〇〇を導くためには、△△が必要なので、それを決めるための基準として、××から決めませんか?その次に□□について考えましょう!」
「個人ワークで考えたアイディアを先に共有しても結局議論中に手戻りしてしまうので、まずは進行方法を決めて、段階ごとに皆さんの思考プロセスを共有しませんか?」
②受容性
受容性に関しては、たとえ議論の足枷になると感じられてしまうメンバーがいたとしても、見捨てずにチームワークを発揮させようとすることが有効だと考えられます。GDの経験が豊富な就活生にとって、初歩的なミスはストレスになりますし、間違いを指摘されたメンバーは萎縮してしまい、発言が減少してしまうかも知れません。ここでアピールすべきことは、どのような不確実性でも受け入れ、後の議論に活用することです。
発言例:
アイディアベースの議論になりそうだったが、軌道修正した場面:
「まずは〇〇について議論しましょう。ただ、今のアイディアは素敵だと思うので、後で取り入れましょう!」
軌道修正後に、議論している場面:
「それこそ、最初に〇〇さんが出してくれたアイディアはこの課題解決に直接生かせると思います!」
ケースB:自分がアピールしたい役割やキャラクターが他人と重複した時
この場面は、経験を積み、立ち回り、適正などを理解して自分なりのGD攻略法を心得ている就活生が陥りがちな場面です。例えば以下のような場面が挙げられます。
- ファシリテーターが得意で立候補したが、他にもやりたいメンバーがいる場合
- 形式的な役割を持たずに議論を根回しすることが必勝法だったが、そのようなメンバーがもう一人いる場合
これらのような場面は自分にとって不確実な状況ですし、チームにとっても役割が重複してしまうと議論が非効率になるため、対応が必要です。ここで解決に有効なコンセプチュアル・スキルは、④多面的視野、⑥柔軟性、⑩俯瞰力の3つの要素です。
※以下では説明の都合上、④柔軟性と⑥多面的視野の説明順を入れ替えています。
⑥柔軟性
この状況における柔軟性とは、一つのGD内でチームの状況に合わせて自分の役割を変えるという意味です。
チームのメンバーは、GDで一つの成果物を作るという意味では仲間ですが、選考という意味では競い合う相手であるため、自分の得意な立ち回りをしたり、議論を誘導したりしたくなるものです。しかし、複数のメンバーが暗黙的に自己中心的な行動・言動を取った場合、面接官視点からは見透かされてしまいます。そのため、チームを陰から融和し、チームワークを促進することで差別化することができます。
④多面的視野
「柔軟性を示すだけで大丈夫なの?」と思う読者の方もいたのではないでしょうか。
役割やキャラクターが重複した場面では、柔軟性と多面的視野の組み合わせで、より他の就活生と差別化できると考えられます。多面的視野とは、一つの物事に対して複数のアプローチを行う能力のことです。GDにおいては、一つの成果物を生み出すために、複数の役割をこなすということを意味します。
以下に例を挙げます。
- 書記を行いながら話をまとめたり、メンバーの意見にツッコミを入れたりする
- タイムキーパーを行いながら、ゴールから逆算し、論点の粒度を考える
GDでは、形式的な役割を予め決定してから議論する場合が多いですが、その役割には難易度に差があります。書記やタイムキーパーといった役割を持つメンバーはマルチタスクを行うため、担当する役割のないメンバーよりも議論に集中することが難しいためです。しかし、面接官は何度も就活生のGDを見ているため、その差は理解しています。そのため、難しい役割を担当しながら多面的に議論に貢献することができれば、面接官は適切に評価してくれるはずです。
⑩俯瞰力
俯瞰力は、柔軟性と多面的視野を活用するために必要な能力です。
そもそも、柔軟に役割を変えたり、チームに必要な役割を複数こなしたりするためには、チームの状況を理解する必要があります。GDは選考であるため、就活生は、周りが見えなくなってしまうことがあります。議論が白熱する時こそ、落ち着いて周囲の状況を認識することが、不確実性への対応という有能な人材に必要な能力として、非常に重要だと考えられます。
ケースC:メンバー全員が同じ方向を向いて議論できていない時
この例としては、以下が挙げられます。
- メンバーの総意を取ることができていないのに議論を進行させてしまう場面
この場合に注意すべきことは、「認識のズレ」です。GDにおいてチームワークが必要不可欠であることは多くの就活生が認識しているため、意図的に「一匹狼」として振る舞うことは少ないと考えられます。
その前提の下、メンバー全員が同じ方向を向いて議論できていない原因は、認識のズレにあると考えられます。例えば、あるメンバーは議論がまとまったと考えていても、別のメンバーはそのように考えていない場合などです。このような場合には、本質的には対立していないものの、対立的な構図が表象されてしまい、指摘しづらい雰囲気が生まれてしまいます。ここでアピールすべきコンセプチュアル・スキルは③クリティカルシンキング、⑨チャレンジ精神の2つです。
③クリティカルシンキング
クリティカルシンキングは、批判的思考とも呼ばれ、客観的に物事を判断し、本質を捉える能力のことです。
私の主観ですが、コンセプチュアル・スキルの中でこの能力を持つことが、就活生にとって最も難しいのではないかと考えています。何故なら、一度きりの選考においてクリティカルシンキングはハイリスクだと捉えられるためです。
GDのゴールは一つの成果物を出すことで、そのためにチームワークの活用が求められると説明しましたが、「チームワーク」と「批判的思考」は対極にあるように感じられてしまいます。従って、批判的思考をすることでたった一回の選考を失敗することは勿体無いという心理が働いてしまいます。一方で、就活生にとって持つことが難しい能力だからこそ差別化することができます。
また、当社マネージャーも「批判的思考に慣れていない若手が多いからこそ、他人の意見を聞き、自分の意見を言うことができる人には価値があります。」と述べており、批判的思考力の大切さが窺えます。
発言例:
認識が統一されず、議論が曖昧なまま進みそうな場合:
「認識が統一されていないと思うので、〇〇の定義を再確認しませんか?」
特定のメンバーだけで議論が進みそうな場合:
「総意が取れていない気がするのですが、もう少し皆さんの意見を聞いてみませんか?」
ケースD:議論の進行が滞った時
この場面の具体例としては、以下が挙げられます。
- 本来議論すべき内容と論点のずれた議論がなされている場合
- アイディアの出し合い、議論を深めることができていない場合
- 手戻りが発生しそうな場合
GDでは、前提条件を定めた上で議論することが求められるため、上記のような場面は好ましくない場合が多いです。しかし、これに該当する場面は、必ずしも、議論に悪影響を与えるとは限りません。そもそも前提条件が不適切であることを議論の進行中に認識したり、議論が行き詰まってしまったりする場合には、上記の場面が議論を活性化させる可能性があるためです。
この内容を踏まえ、コンセプチュアル・スキルと照合させると、①ロジカルシンキング、⑦知的好奇心、⑧探究心要素の3つの要素が、このような場面への対応に有効です。
①ロジカルシンキング
ロジカルシンキングは、混乱しそうな議論を軌道修正させることに有効であると考えられます。
論点のずれた議論がなされている場合には、GDのゴールとそれに必要な要素から議論が乖離していることを示すこと、ロジカルシンキングをアピールできます。また、論点のずれが前提の間違いを示唆している場合もあります。その場合は、GDのゴールや残り時間から逆算し、前提条件を修正するか、そのまま議論を進めるのかを判断することに有効です。(前提を覆すこと自体は良いことではないので要注意)
発言例:
前提条件や議論の進行方法のずれを認識し、修正を提案する場合:
「この前提条件/議論の進行方法だと、結論に必要な〇〇を詰めることができないので、まだ時間もありますし、この前提条件/議論の進行方法を決め直しませんか?」
他のメンバーが前提条件や議論の進行方法のずれを指摘したが、反対意見を述べる場合:
「確かに、その前提や議論の進行方法を考え直した方が、議論を深めることはできると思いますが、現状目的に必要な議論はできていますし、残り時間で議論し直してアウトプットを完成させることは難しいと思うので、このまま進めませんか?」
⑦知的好奇心・⑧探究心
知的好奇心は、知らないことに興味を持ち、知る能力のことで、探究心は、物事の深い知識を得たり、原因を解明したりしようとする能力を表します。
知的好奇心と探究心は、意見に論点のずれやアイディアベースのものがあった場合に、これらを適切に議論へ利用することでアピールできます。前提条件に基づいた合理的な議論の最中に、論点のずれた意見やアイディアベースの意見が発せられると、議論が滞ることが多いです。そのため、もし知的好奇心や探究心がなければ、効率化のためにこれらの意見を検討せず、無駄にしてしまう可能性があります。しかし、そのような意見を活用することができれば、議論をより深めることができるため、知的好奇心と探究心は大切なスキルです。
発せられた意見に対して、その論点がずれていた場合、考え方をシフトし、議論と目的との整合性を取り、アイディアベースの意見だった場合、その本質を問うたり、背景をメンバーから引き出したりすることが有効です。
発言例:
意見の論点がずれていた場合:
「Aさんのアイディアは、抽出した課題解決からは少しずれていると思うのですが、アイディアの△△の部分は活かせると思うので、もう少し議論して、部分的に取り入れるのはどうですか?」
意見がアイディアベースだった場合:
「Bさんのアイディアは、課題の〇〇な点がまだ考慮されていないので、そこを深掘りしませんか?繋がりが可視化されれば、良い解決策になると思います!」
いかがでしたでしょうか。この記事が皆さんのグループディスカッションを成功させるヒントになれば幸いです。
<執筆:渡辺 藍>
※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。