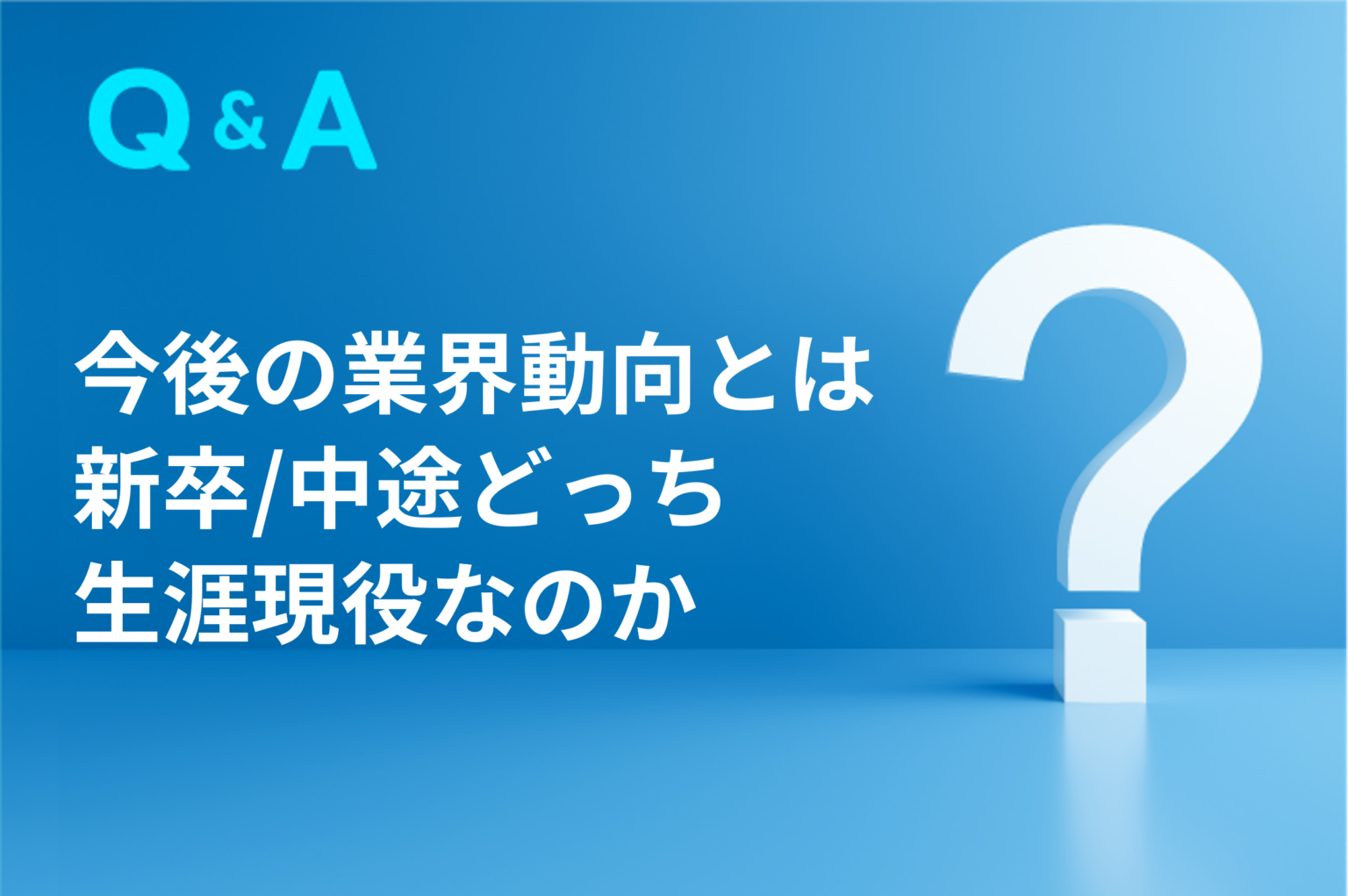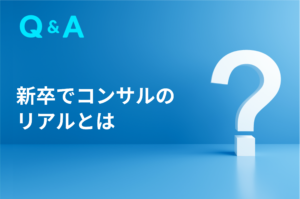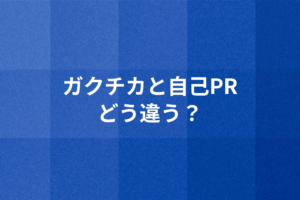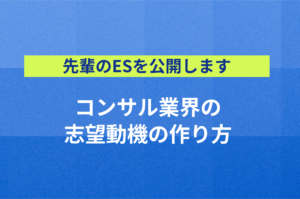Q1. コンサルティング業界は、これからどうなるの?
A.IT領域がより顕著にメインになってきます。その反面、IT人材の不足が課題として挙げられます。
これまでコンサルティング業界は主に「会社の経営を改善する」ことを目的に、【戦略立案・構想策定〜システム開発・導入】までの、いわゆる、上流〜下流のサービスをクライアントに提供してきました。その中で、今までのITコンサルタントは、「会社の経営を改善する」という目的に対する手段を提供する人材として、サービスの下流部で活躍していたと言えます。
しかし、今では革新的なIT技術の進化により、「IT技術あっての経営」へと変わってきており、IT技術を用いた経営改善の可能性を追求する中で、「IT技術ファースト」で経営課題と向き合うようになってきました。言い換えると、かつての経営を改善するという目的とIT技術を用いて解決するという手段が逆転、ないしは一体化してきています。そのため、上流の戦略側から経営課題にアプローチしていたコンサルタントは下流であったIT領域も取り扱うようになり、逆に下流のIT領域を取り扱っていたコンサルタントも戦略の分野も担う傾向にあります。
この直近の変化により、より多くのIT人材がコンサルティング業界に必要となりました。しかし、IT人材は世界中で不足しているのが現状です。仮に、新たなITシステムが誕生したとしても、世の中の会社に対し、迅速にそのシステムを浸透させるだけの知識・技能を持ち合わせたコンサルタントの母数が足りていないのが現状です。
そのため、近年、【戦略立案・構想策定〜システム開発・導入】を一気通貫でクライアントに提供する、大手総合ファームが新卒入社の採用人数を増やす傾向にある背景には、上記の変化があると考えられます。
Q2. コンサルタントは新卒入社と中途入社どっちがいいの?
A.最終目標をトップコンサルタント(マネージングディレクター)になることに置いた場合、どちらでも良いです。
コンサルティングスキルを磨くことで昇格できるのは、マネージャー(事業会社で課長に相当)までと言われています。その先のトップコンサルタント(マネージングディレクター)として活躍するには、依頼された案件を受け持つだけでなく、自らクライアントから案件を獲得する力が必要になります。案件を個人単位で獲得するためには、プロフェッショナルなコンサルティングスキルと共に、特定の事業分野に対する専門的知見を有し、そこに顧客から信頼を寄せてもらうことが大事です。双方を習得するにはそれぞれ、コンサルティング会社、事業会社で実際に働くことが一番の近道と言えるでしょう。
そのため、トップコンサルタントになることを目標に置いた時、以下の2通りのキャリアパターンが考えられます。
①コンサルティング会社に新卒入社し、顧客・案件を通じて専門知見を深めていく
②事業会社で実務経験を通じて専門知見を習得した後に、コンサルティング会社へと中途入社
どちらも、トップコンサルタントとして得なければならないスキル・知識を獲得する順序が入れ替わっているだけであり、どちらが良いかは個人個人によって違うと言えます。既にある特定の事業領域に興味のある方は事業会社、これからそれを見つけていこうという方はコンサルティング会社に先に入社するのが良いでしょう。
Q3. 生涯コンサルタントの人はどのくらいいるの?引退時期は?
A. 現状はあまりいません。しかし、今後コンサルタントとして定年まで働く人は増えてくる可能性が高いです。
かつてのコンサルティング業界では、”up or out”※という言葉があったように、マネージャーより上の位に昇進できないコンサルタントたちは、退職するという風潮がありました。しかし、近年では、働き方改革をはじめとした社会的情勢の変化により、”up or out”の風潮も無くなりつつあります。
その上、前述の通り、IT人材の不足に伴い、現在コンサルティング業界は人員の拡大傾向にあります。これらを考慮すると、今後コンサルティング業界においてボリューム層になるであろう、今の若手世代の中には、そのまま会社に残り続ける人も増え、定年まで働く人の割合は今よりも増える可能性が高いと言えます。
一方、現在のコンサルタントのキャリアとして多いのは、事業会社へと転職するパターンです。コンサルタントとして、幅広い業界領域を扱う中で、特別興味が湧いた領域の事業会社へと自ら転職する場合もあれば、クライアント先でプロジェクトを共にした社員の方にヘッドハンティングされる形で、転職するケースも多いです。
※ “up or out”: 「昇進(up)するか、そうでない場合は退職(out)するか」という意味
<執筆:白濱 恭太郎>
※本記事掲載の情報は、公開時点のものです。